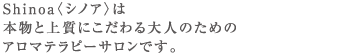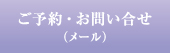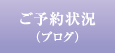日本の香り文化~④追風(おいかぜ)
本物と上質を求める大人のためのアロマテラピーサロン「アロマテラピー&リラクセーション Shinoa」のブログにお越しいただきありがとうございます。
国風文化の花開いた平安時代の王朝人の「香りの使い方」についての第4回目です。

今回は、「追風」です。
衣装に焚きしめた香りや忍ばせた匂い袋の香りが、その人が動いたりすれ違ったりするときに風に乗って漂ってくること、またはその香りのことを言います。
『源氏物語』の「若紫」に印象的な場面があります。
光源氏は瘧病にかかり、まじないや祈祷など試みたものの思わしくありませんでした。
そんな時、よく病気を治す僧都がいると聞いて、北山に出向くことにしました。光源氏は、ここで後の妻となる紫の上を垣間見ます。
彼女はこの時はまだ10歳ほどの子供でした。
僧都の住まいは、草木は整えられ、遣水には篝火を灯し、灯篭も風情よく、こざっぱりと整えられています。
そして、そこに漂う香りの表現が秀逸です。
そらだきもの、いと心にくく薫り出で、名香の香など匂ひみちたるに、君の御追風、いとことなれば、内の人びとも心づかひすべかめり。
空薫物が奥ゆかしく香ってきて、仏前の名香も一面に漂っている中に、光源氏の衣装に焚きしめられた香りが格別で、奥にいる人たちも気を使っているらしい。
空薫物は、どこからともなく香ってくるように室内空間に焚く香であり、日常使う中で調度品などにも香りが染みつくものです。
この場面では、空薫物が香り出て、仏前に捧げられた質の良いお香が漂い、さらに光源氏自身の香りが「追い風」として香るということで、3種類の異なる香りが、動きを持って混ざり合う様子が見事に表現されています。
吉海直人氏(同志社女子大学名誉教授)は、
「無風状態の中、源氏が歩くことで空気がわずかに乱される。
その微妙な乱れによって、源氏の衣装に焚き込められた薫りが、源氏の周囲に拡散するのである。
これぞまさに平安貴族の雅な世界の具現ではないだろうか。」と述べています。<「『源氏物語』の薫りを読む」新典社選書より抜粋>

『徒然草』においても、
寝殿より御堂の廊に通ふ女房の追風用意など、人目なき山里ともいはず、心遣ひしたり
寝殿から仏事が行われる御堂の廊下を行き来している女房達が、着物にたきしめた香りを漂わせているのは、人のいない山里にもかかわらず、心憎い心遣いだ。
とあります。
ぷんぷんと匂うのではなく、風の動きにより香りが動くことを素晴らしいと感じるのが日本人の感性だったのですね。
当教室では、
を随時開講中です。
本コースでは、日本人が親しんできた香りを味わい、香り文化や歴史を学びます。
このコースは、単発受講も可能!
古に思いを馳せつつ、自分だけの香りを調合する豊かな時間を味わってください

<講義内容>
1.日本における香りの歴史
2.日本人と香り<源氏物語>
3.日本人と香り<香道>
4.日本の国土と香り
5.お香材料と和精油
<和のアロマクラフト作り>
1.練香
2.塗香と香袋
3.置き香と香りストラップ
4.練り香水(ソリッドパフューム)
5.和菓子のアロマストーン
<受講料>
1)コース(5回)でのお申込み
42,800円(材料費+税を含む)全5回(約10時間)
2)単発(1回)でのお申込み
9,000円(1回)
*単発で1回ご受講の後、コースでの受講に切り替えられた場合には、コース価格でご受講いただけます。
お一人様から、ご都合の良い日時で随時、開講します。
お申込み、お問合せをお待ちしております。