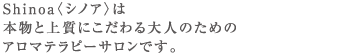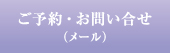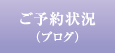日本の香り文化~③えび香
本物と上質を求める大人のためのアロマテラピーサロン「アロマテラピー&リラクセーション Shinoa」のブログにお越しいただきありがとうございます。
国風文化の花開いた平安時代の王朝人の「香りの使い方」についての第3回目です。
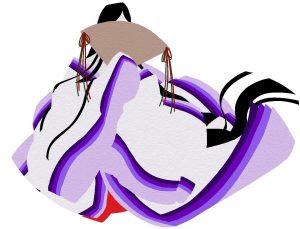
今回は、「えび香」です。
様々な香料を砕いて調合し、袋に入れて衣装に下げたり、衣装箱に入れて防虫や香り付けに用いた匂い袋のことです。
最古の匂い袋と言われるのが、正倉院にあるえび香で、神護景雲二年(七六八)の年紀がある香袋に入っています。
時代が下って、江戸期には「花袋」「浮世袋」などと呼ばれる匂い袋が流行しました。
『源氏物語』では「末摘花」のえび香が印象的です。
君は、人の御ほどを思せば、「されくつがへる今様のよしばみよりは、こよなう奥ゆかしう」と思さるるに、いたうそそのかされて、ゐざり寄りたまへるけはひ、忍びやかに、衣被の香いとなつかしう薫り出でて、おほどかなるを、「さればよ」と思す。
光源氏は、相手のご身分を推量なさると、「当世風の軽々しいよりは、この上なく奥ゆかしい」と思い続けていたところ、たいそう勧められて、いざり寄っていらっしゃる様子、もの静かで、えびの薫香がとてもやさしく薫り出して、おっとりとしてしているので、「やはり思ったとおりであった」とお思いになる。
末摘花は亡き常陸宮の姫君という高い身分ではありましたが、決して姿の美しい女性ではありませんでした。
常陸宮が亡くなった後の生活は困窮し、住まいも荒れ、着物も随分と古びています。
しかし、身にまとう香りは、高貴な姫君ならではのすばらしさで、光源氏に「さすが」と思わせるのです。
その香りは、末摘花が自分の衣服に香りを移したのえび香でした。
このシーンの後も、末摘花が語られるとき、彼女のまとう香りの格式の高さも語られるのです。
当教室で開講している「お香材料と和精油を楽しむ『和アロマコース」でも、お好みの香材料をブレンドしたオリジナルの匂い袋を作ることが出来ます。
このコースは、単発受講も可能!
古に思いを馳せつつ、自分だけの香りを調合して匂い袋を作ってみてください。

当教室では、
を随時開講中です。

<講義内容>
1.日本における香りの歴史
2.日本人と香り<源氏物語>
3.日本人と香り<香道>
4.日本の国土と香り
5.お香材料と和精油
<和のアロマクラフト作り>
1.練香
2.塗香と香袋
3.置き香と香りストラップ
4.練り香水(ソリッドパフューム)
5.和菓子のアロマストーン
<受講料>
1)コース(5回)でのお申込み
42,800円(材料費+税を含む)全5回(約10時間)
2)単発(1回)でのお申込み
9,000円(1回)
*単発で1回ご受講の後、コースでの受講に切り替えられた場合には、コース価格でご受講いただけます。
お一人様から、ご都合の良い日時で随時、開講します。
お申込み、お問合せをお待ちしております。