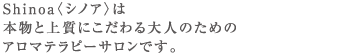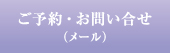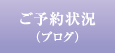和のアロマを学ぶ意味
本物と上質を求める大人のためのアロマテラピーサロン「アロマテラピー&リラクセーション Shinoa」のブログにお越しいただきありがとうございます。
昨日のブログで、来月以降開講する
についてのご案内をしました。

その中で、「日本産精油(和精油)を積極的に取り入れる中で、私たちの祖先が嗅いできた香りは、より効果的に私たちの脳に影響を及ぼすことを私は実感していたからです」と書きました。
今日はそれについて、詳述したいと思います。
少し長くなっていますが、本コースにご関心をお持ちの方は、どうぞご一読ください。
◆植物利用の歴史と「和のアロマ」を学ぶ意味◆
私たち人類は、様々な方法で植物を活用して生きてきました。食料として、家畜の餌として、建材や衣類の材料として、燃料として、そして医薬品や化粧品として等、人類の歴史は植物利用なくしてはありえません。さらに美しい花の姿やその香りに心癒されてきました。
2017年、スペインのエルシドロンで48000年前のものとみられるネアンデルタール人の集落が発掘されました。そこでは、激しい痛みを伴う歯性膿瘍を患い、腸内に激しい下痢を引き起こす寄生虫を抱えていたネアンデルタール人の青年が、抗生物質を産生するペニシリウム属の真菌や、鎮痛効果のあるサリチル酸を含むポプラの木の破片を噛んでいたことが発見されました。すでに、ネアンデルタール人が「フィトテラピー(植物療法)」を生活に取り入れていたことがわかります。
約5000年前、古代エジプトでは乳香(フランキンセンス)や没薬(ミルラ)などが使われていましたし、約2500年前に古代ギリシャで活躍した医学の祖、ヒポクラテスは香油を使ったマッサージや薬草療法を行ったとされています。また、新約聖書には、キリスト誕生の際に東方の3賢人が、黄金と乳香と没薬をささげたと記されています。
水蒸気蒸留法を用いて、芳香蒸留水を得ることができるようになり、さらには現在使われている精油に近いものを作ることが出来るようになったのは11世紀のアラビアでした。18~19世紀にかけて化学が急速に発展し、自然原料から単独の化学物質を抽出したり、全く異なる物質を反応させて新たな物質を合成できるようになるまでは、身近な植物を様々な形で用いて病気を予防したり治療してきたのです。
化学の発展により一時衰退した植物利用は20世紀に入り見直されるようになりました。体に起こる不調を部分としてとらえるのではなく、心も含めた全人的なものとして捉える「ホリスティック」な考え方で精油を用いる試みがイギリスを中心に広がりました。フランスでは精油の持つ様々な薬理効果を利用して医療の場で役立てる方向に発展しました。
近年、高齢化社会の進行、生活習慣病やストレスによる心身の不調などが深刻化する中において、日本でもアロマテラピーの効果検証に関わる研究は急速に進み、心身の健康に役立てようとする人々の関心を集めています。
日本では古くから、菖蒲湯や柚子湯など香りで邪気を払う習慣がありました。また6世紀に、仏教とともに中国から伝わったお香が日本文化に根付き、独自の発展を遂げてきました。ただし、主に西欧で発展を遂げてきたアロマテラピーが、日本で一般に普及したのは1990年代半ばであり、今も普及している多くの精油が外国産です。そんな中、近年、森林や農産物を守る取り組みとともに、日本各地で様々な和精油(国産精油)が作られるようになっています。
「身土不二」という言葉があります。「その土地でできたものを食べていると健康が保たれる」という考え方です。私たちはその住む土地の食物や風土によって生かされて育まれた歴史があるのです。
私たちの祖先が、嗅いできた香り。
それは森に漂う木々の香り、咽喉を潤したかんきつ類の香り、あるいは、唐から伝わった貴重かつ憧れの香りかもしれません。私たちの脳に深く刻まれたそれらの香りをアロマテラピーとして取り入れることは、香りにおける身土不二になるのではないでしょうか。
2013年にアメリカのエモリー大学の研究チームが興味深い研究報告を行いました。
研究チームは、マウスに一定の香りを嗅がせたうえで電気ショックを与えることで、匂いだけで恐怖を感じる条件付けを行いました。すると、条件付け、すなわちその匂いを嗅ぐと恐怖反応を示すという行動が、そのマウスだけでなく、子世代、孫世代にまで伝わったのです。これは香りの記憶が次世代以降に引き継がれることを意味し、「獲得形質は遺伝しない」という生物学のセオリーを覆すことになりました。
和の香りは、それは優しく、懐かしく、心にすーっと染み込んでくるようです。
このコースでは、日本における香り文化や歴史について学び、和精油や、香材料(刻み香)に触れ、それらを日常生活で活用できるためのアロマクラフトを作成します。
心身の健康と心豊かな毎日のため、祖先から引き継がれた和の香りを生かしましょう
また、アロマレッスン(講座)やワークショップを主宰している方には、さらなるメニューの豊富化にもお役立てください。